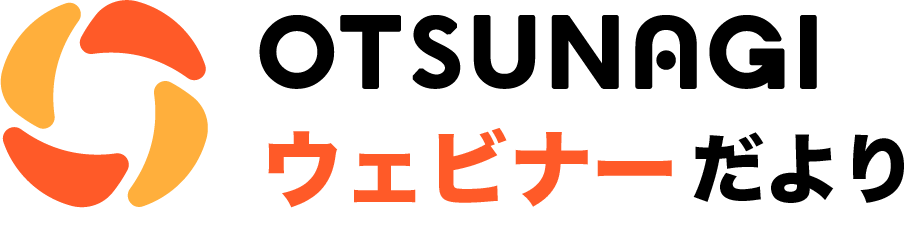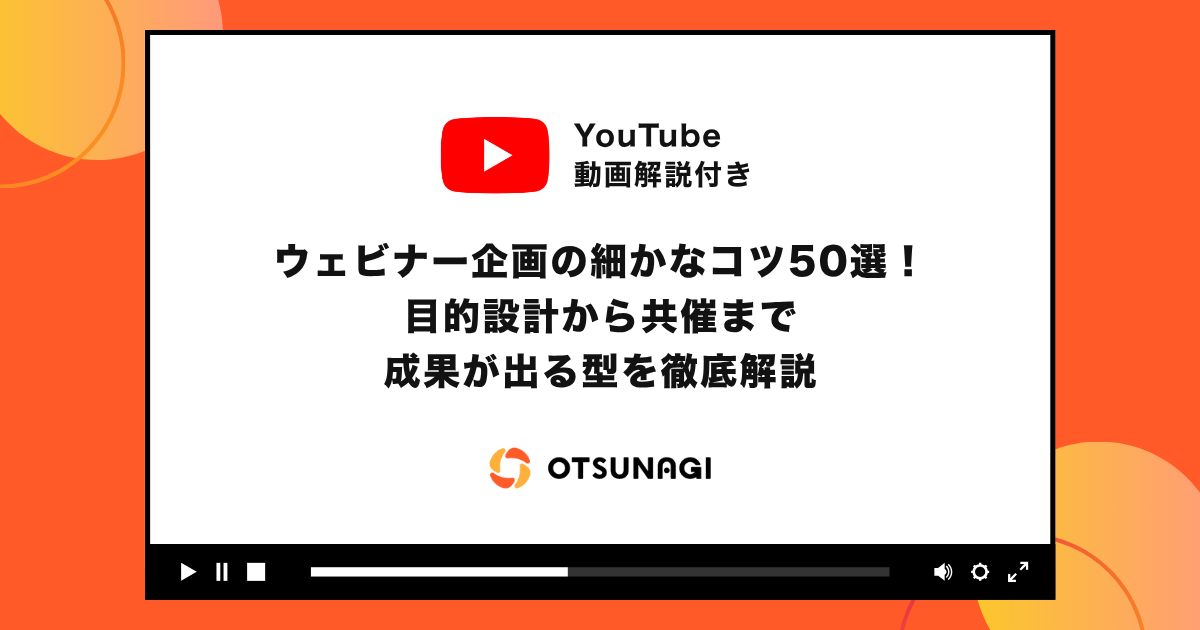ウェビナーを担当していると、「集客できる企画を作りたい」「企画のコツって何?」「他社でうまくいってるコツを知りたい」と思うことは多々あるのではないでしょうか。ウェビナーの成果は「企画」で決まると言っても過言ではありません。
本記事では、成功のポイントを5つの視点に分けて「細かなコツ50選」をご紹介します。筆者が300回超の企画・登壇、50社以上の開催支援を行ってきた実績にもとづき、様々な経験談をもとにコツを解説します。
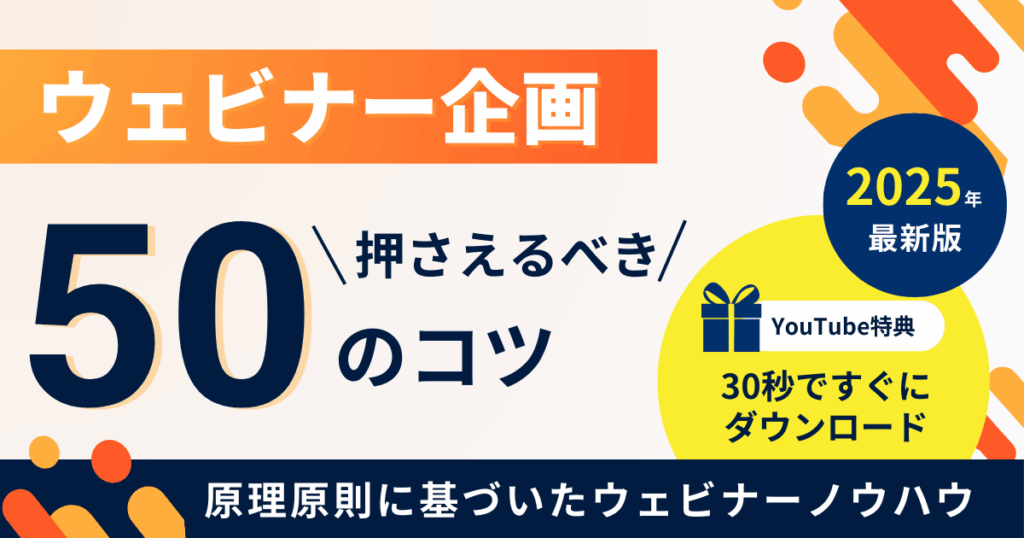
OTSUNAGI特製のウェビナーコツ50選を無料でプレゼントいたします!
以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。
なお、本記事の内容は下記の動画でも解説しております。併せてご活用ください。
ウェビナーの企画と目的設定
① 開催目的は3種類に分けて考える
1つ目が認知拡大・新規リード獲得、2つ目が見込み顧客の育成・相談設定、3つ目がブランディングです。まずはこの3つのどれかに側した企画を立ててみてください。
② 企画は「必要性」と「飢餓感」をもたせる
「必要性を見出すこと」と「飢餓感をもたせること」が重要です。こうすることで「もっと知りたい」「商品を欲しい」と思ってもらえる構成になります。
③ まずは“1人を大満足”させる
ウェビナーは7割が“ながら見”で全員満足は難しいため、1人を大満足させる企画を作ることが大事です。全員に伝えようとするほど、訴求軸がブレたり抽象度が上がったりするため、伝わらないウェビナーになってしまいます。
④ 「なぜ満足できるのか」に答えられるウェビナーにする
自社にしかできない企画を用意すると満足度が上がり、ひいては商談設定につながりやすくなります。
⑤ 「既に売れている型 × 新しい要素」で企画をつくる
0から新しい企画というのは、そうそう生まれません。うまくいっているコンテンツを抽象化し、パターン化して、そこに新しい要素を加えれば良いのです。
例えば、Instagramのアルゴリズムを解説するセミナーを抽象化すると、「最新の情報をお伝えする」という型になります。その型を弊社に当てはめると、ウェビナーの実態調査を行い、最新情報・データを解説するウェビナーに変わります。このように、他社で既に成功している企画を抽象化し、各社の要素を加えるだけで十分良い企画に仕上がります。
⑥ 既視感のない登壇者の組み合わせで実施する
人選はかなり重要です。「見たことがないものを見たい」という好奇心を駆り立てる組み合わせが、内容をさらに良くする可能性があります。
⑦ ウェビナーは独自性を出しやすい
無料で作れて無料でできる企画なので、タイトルやテーマにどんどん新しい要素を入れてチャレンジし、成功・失敗を重ねてください。
⑧ 独自性の源泉はトレンド・一次データ・体験向上
トレンドを用いる、自社の一次データや経験で解説する、生放送で質疑応答やブレイクアウト相談会を設けるといった体験設計が、貴社の独自性につながります。
例えば、以前カスタマーサクセス・カスタマーサポートの人が登壇をして、顧客の成長のステップを具体的に話しているウェビナーに参加しました。一般的にはマーケティング部や営業部の人が登壇するケースが多いですが、カスタマーサクセスの方の登壇ではより具体性・ストーリー性があり、楽しいウェビナーでした。
⑨ 事例ウェビナーは、導入企業の担当者/CSとMCで行う
サービス導入企業の担当者と、自社のカスタマーサクセス/カスタマーサポート、さらに別でMCを設けると、より良い企画にできます。
⑩ 目的は“第一想起”の獲得
情報量が爆発している現代において、ウェビナーから直接大量に受注することは難しいです。役立つ情報を提供してファンになってもらい、困った時にまず思い出される状態を目指すことが大切です。また、ウェビナーを行う目的はチーム内で必ず共有し、浸透するよう努力しましょう。
⑪ コンサル・士業系は「もっと知りたい」で終える
コンサル・士業系のサービスは、視聴後に“もっと知りたい”という状態を作ることが大事です。ウェビナーだけで完結させず、次のアクションにつながる終わり方にしましょう。
⑫ ターゲットは「○○社の○○様」まで絞る
ターゲットは具体的に名指しするレベルで絞らないと、本当に刺さるコンテンツは企画できません。
⑬ 細かいターゲティングで離脱防止
ふわっとして誰にも刺さらない内容は、離脱されてしまいます。内容を絞って濃くすることで、見続けられるコンテンツになります。
タイトル・開催日時・集客について
⑭ タイトルで集客は大きく変わる
ファーストビューで「面白そう」と思わせるには、タイトルとバナーが非常に重要です。自社デザイナーに相談し、妥協せず注力してみてください。
⑮ タイトルは本のタイトルを参考に
書籍のタイトルを参考にすると、アイデアが浮かびやすくなります。
⑯ タイトル詐欺は禁止
タイトルと内容に一貫性がないと、結局離脱されてしまいます。誇大に見せようとしないで、等身大のタイトルを設定してください。
⑰ 良かったタイトルはキーワードで保存・検証
結果の良かったタイトルを振り返り、キーワードをピックアップして保存してみてください。例えば弊社では、「ウェビナー」「ナーチャリング」などのキーワードが、ターゲットが集まりやすい傾向があります。
⑱ 無料集客の最大化=母数×旬なネタ×独自性×リストの鮮度
費用をかけずに最大限集客するには、「アプローチ母数 × 旬なネタ × 独自性 × リストの鮮度」を最大化することが大切です。
⑲ 安易な参加特典は不要
Amazonギフトなどの特典を付けると、関係のない人が来てしまう可能性があります。安易な特典は、必要ありません。ただし、オフラインイベントの場合は効果を発揮する場合もあります。
⑳ 月曜・金曜の開催は避ける
月曜日と金曜日は参加率が落ちるため、ウェビナーの開催は避けた方が良いです。
㉑ 曜日や時間は本質的には関係ない
人は見たいものを優先して見ようとするため、本質的には曜日や時間は関係ありません。ターゲットによって見やすい時間を選定することが大切です。
㉒ 企画〜開催は2ヶ月設ける
企画から開催まで、2ヶ月を確保するようにしましょう。集客期間として、最低1ヶ月は設けるためです。
㉓ 唯一無二の内容で集客する
他でも聞けると思われる内容は、集客しづらいです。唯一無二の企画を意識してください。
㉔ 一歩先のトレンドを掴む(X/PR/広報の発信)
XやFacebookの業界詳しい広報担当の発言、PR TIMESやプレスリリースを見て、次に来るトレンドや話題を把握してみてください。
㉕ 午前開催がベスト
当日にターゲットリストへアプローチし切れるため、午前中の開催がベストです。ただし接続率はターゲットによって変わります。
例えば弊社では、17時〜18時半の接続率が高いため、15時や16時にウェビナーを開催をすることがあります。
放送形式と参加者エンゲージメント
㉖ 放送形式と開催方式のパターンを把握する
放送形式は「生放送・アーカイブ録画放送・疑似ライブ放送」、開催方式は「ディスカッション型(対談)・プレゼンテーション型・インタビュー型」といったパターンがあります。対談や掛け合いがあるほど、視聴者の満足度は高まる傾向にあります。
㉗ ディスカッションは“その場での面白い回答”が鍵
企画時点で流れは用意しつつ、過度な台本の作成は避けるのが良いでしょう。登壇者の技量にもよりますが、大枠だけ決めて詳細は決めすぎないほうが良い対談になりやすいです。ただし、落とし所は必ず用意するようにしましょう。
㉘ 目的に合わせて開催方式を選ぶ
ウェビナーの開催目的に合わせて、生放送・アーカイブ録画放送・疑似ライブ放送、ディスカッション型(対談)・プレゼンテーション型・インタビュー型の使い分けを行ってください。
㉙ ゲーミフィケーションで双方向性を高める
冒頭に投票機能を用いて視聴者に投票してもらったり、オープンクエスチョンを差し込んだり、その場で来た質問を広げたりなど、双方向性を持たせることで参加度を高めます。
㉚ 10分に1回はノウハウを散りばめる
ウェビナーは”ながら見”の割合が非常に多いです。画面を何回も見てもらえるよう、10分に1回はノウハウを散りばめることで、印象付けを強化します。
㉛ 申込フォームや投票結果はPR・記事化に転用する
申込時点の設問やウェビナー中の投票結果を、プレスリリースや記事にするのがおすすめです。調査データと変わらない内容になり、活用幅が広がるので、アンケートはぜひ積極的に実施してみましょう。
㉜ 録画視聴で質問してくれる人にはしっかり対応する
録画とわかりながら動画を最後まで見て、さらに質問してくれる人は、見込み顧客である可能性が高いです。そういった方には、しっかり後日対応をしましょう。
運営の工夫と成功のポイント
㉝ 登壇内容の最後には必ずまとめを入れる
ウェビナーは、“ながら見”が7割と言われています。最後にまとめの章を作るだけで、伝えたいことが伝わるようになります。
㉞ 「とてつもなく勉強になる」内容かをチェック
再度見返したいと思ってもらえる企画かどうかを、最後に確認するようにしましょう。
㉟ 見返されるのは“心理変化”ではなく“行動変化”を促す内容
「〇〇だと思います」ではなく、「この成果を出すにはこれをしてください」と言い切るコンテンツは、何回も見られます。
㊱ LP・バナー・メール・登壇内容・資料で使用する言葉を一貫させる
申し込みページ、バナー、メール、登壇内容、資料で使う言葉は一貫性を持たせてください。一貫性を持たせることで、印象に残りやすくなります。
㊲ 慣れてきたらタスク管理ツールはいらない
ウェビナーは1〜2ヶ月の短いプロジェクトのため、1つ1つ管理すると煩雑になります。一定のスキルがあれば、1人が1企画を全て担当し、ウェビナー担当者を増やして回していく方法がおすすめです。
㊳ 参加=購買意思ではないことに注意
見込み顧客は関心を持っただけで、購買の意思がない場合が多いです。ノウハウが欲しいだけであることが大半で、強引に前へ進めると迷惑になってしまうということを、肝に命じましょう。
㊴ 時間内に“態度変容”のゴール状態を設定する
基本的に、自社のカスタマージャーニー通りにはいきません。ウェビナーは30〜60分いただける施策なので、その時間に必ずゴール状態を設定して、態度変容を起こせるようにしましょう。
共催ウェビナーの企画
㊵ 共催先は「ターゲット配信母数 × 自社サービスとの親和性」で選ぶ
共催先は「ターゲット配信母数 × 自社サービスとの親和性」で選定しましょう。例えば弊社では、ウェビナー担当者の配信リストを多く持ち、集客代行プランを持つ会社とは親和性が高い、という考え方です。
具体的には、弊社は企画代行や録画ウェビナーの制作サービス、ウェビナーの立ち上げコンサルティングを行っている会社なので、集客代行サービスは持ち合わせていません。ですので、集客代行サービスを持ち合わせている企業との共催は非常に相性が良いです。
㊶ 企画書に「何人集めてほしいか」を明記する
共催の場合は特に、集客数の期待値をはっきり書くようにしましょう。
㊷ 共催先を開拓するときは、自社である程度内容を固めてから打診する
何も案がないまま提案すると、相手に考えさせる負荷がかかり、共催許諾をもらいにくくなります。
㊸ 共催先の獲得方法は「マッチングサービス・紹介・アウトバウンドコール・問い合わせフォーム・SNS」
これらは全て、弊社が共催先を獲得する際に使用したことがある手段で、いずれも有効です。今は、共催先マッチングプラットフォームを使うのが最も早く効果的です。
㊹ 共催提案は必須項目を伝える
何の目的なのか・なぜあなたの会社なのか・共催先のメリットは何か・どれだけ共催がしたいのか、を明確に伝えます。
㊺ リソースがある場合は、共催先にToDoを任せない
スケジュールがずれにくく、コミュニケーションコストも下がります。MAツールのデータ項目も揃い、その後のインサイドセールスのアプローチが早くなるため、おすすめです。
㊻ 開催後の取り決めは企画時点で決めておく
申込リストの共有方法・共有範囲・各社からのアプローチのタイミングなどは、企画時点で決めておきましょう。視聴者へのアプローチが多いと、クレームにつながりかねません。
㊼ 目的と相手に合わせて、企画書フォーマットを柔軟に変える
ドキュメントで欲しい企業もいれば、チャットやメッセージで簡易的に箇条書きで欲しい企業もあります。相手に応じて、共催許諾をもらいやすいよう工夫しましょう。
㊽ 理想は、相手が企画書の内容をそのまま話せるくらい具体化する
共催を打診する前には、共催先企業が実際に行っていたウェビナーの内容を把握しておくと、話がスムーズに進みます。
㊾ 共催の打ち合わせは60分いらないことが多い
共催先の担当者のリテラシーにもよりますが、認識が合っていれば短時間で終わらせることが可能です。事前に「30分で大丈夫です」などと伝えておくことで、ハードルを下げられます。
㊿ 共催先は“乗っかる側”で、そこまで積極的ではないと心得る
共催先はあくまで“乗っかる側”で、そこまで積極的ではないと肝に命じましょう。その上で、どうしたら集客やタスクを前向きに実施してくれるかを考え、こまめな状況報告や、相手が嬉しくなるメッセージを送るなど、主催者側が真摯に対応することを心がけてみてください。
まとめ
ウェビナーの成果は「企画」で決まると言っても過言ではありません。本記事でご紹介したコツ50選を参考に、ぜひウェビナーの成果を最大化させてください。
また、案件化するウェビナー企画の作り方を以下の記事で徹底解説しています。併せてご活用ください。
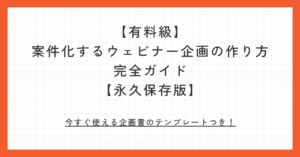
ウェビナー運営にお悩みの方や、成果を最大化したい方は、ぜひOTSUNAGI株式会社にご相談ください。OTSUNAGI株式会社は、年間100件以上のオンラインイベントを支援するウェビナー運営のプロフェッショナル集団です。企画設計からZoom設定、当日の配信オペレーション、アーカイブ活用、さらには共催企業とのマッチングまで、成果に直結するウェビナー施策を一気通貫でご支援いたします。
「社内にリソースがない」「企画が思いつかない」「共催先が見つからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOTSUNAGIにご相談ください。貴社の強みを引き出し、ウェビナーを起点とした“商談につながる仕組みづくり”を全力でサポートいたします。
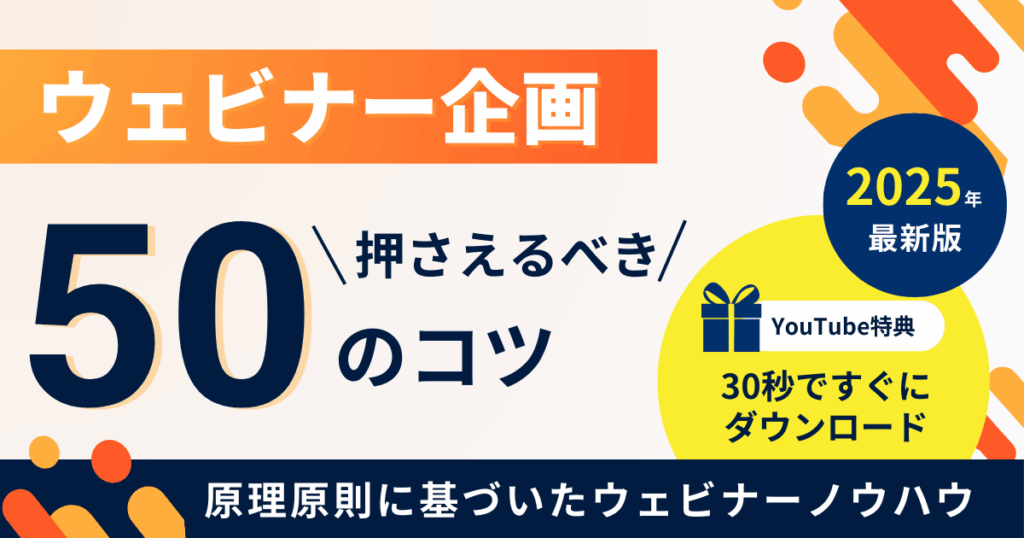
OTSUNAGI特製のウェビナーコツ50選を無料でプレゼントいたします!
以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。