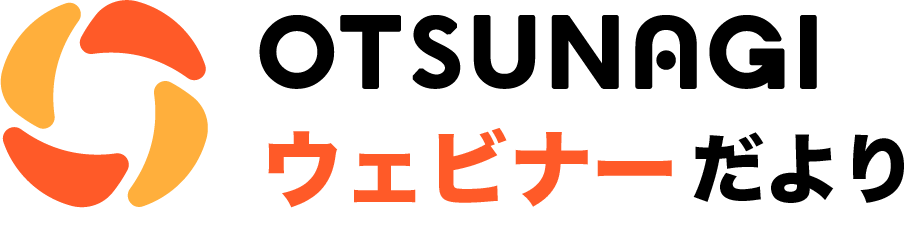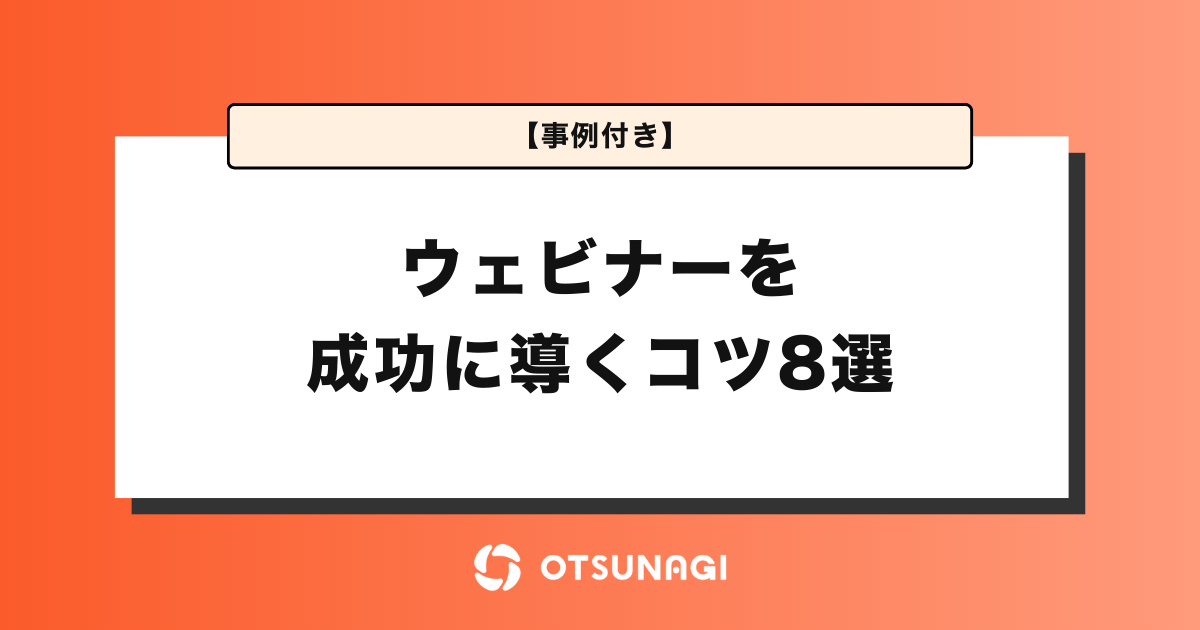マーケティング施策の1つであるウェビナーですが、集客に苦戦している企業も多いのではないでしょうか。集客を成功させるためには、幾つかのコツがあります。
この記事では、弊社のウェビナーやご支援事例から得たノウハウを、8つに分けて解説します。
集客を成功させるためのポイント
ハウスリストを多く持っている企業と共催ウェビナーをする
共催ウェビナーを行うことは、集客を最大化するために有効です。共催ウェビナーというのは、自社以外の会社で2社以上でウェビナーを行うことです。
共催ウェビナーのメリットは、お互いのハウスリストを交換できるという点です。集客目標を設定して相互が集客をすることで、集客数を最大化することができます。2社で行うよりも3社、3社で行うよりも4社で共催した方が集客できる母数が多いのでおすすめです。
ただし、共催先企業数が多ければ多いほど、話す内容が増えるのでウェビナーテーマが抽象的になりがちです。抽象的になると結局どのようなことが学べるかわからなくなり、参加者数は最大化しない場合もあります。
旬なネタで企画をする
旬なネタで企画をするというのは、最も集客数が最大化される方法です。例えば 2024年8月現在であれば AI 関連のテーマや、オリンピックを交えたテーマが該当します。また本記事を執筆している2025年8月現在では、引き続きAI関連のテーマや大阪万博が該当するでしょう。
ここで、「事業再構築補助金」をテーマの一つに取り入れたウェビナーの事例をご紹介します。そもそも補助金のテーマは集まりやすいですが、まさに事業再構築補助金が注目されていた時期だったため、DXと掛け合わせることで非常に多くの方を集めることができました。
また直近で言えば、Chat GPTなどの生成AIと掛け合わせた下記のようなウェビナー などは、通常より2倍ほど多くの方を集めることができました。
旬なネタは、皆様の業種業態に特化した広報の方々に聞くのがおすすめです。もし社内に広報担当がいれば、その方に向こう1年先のトレンドを聞いてみてください。広報の方は先々のトレンドやキーワードを把握しながら活動を行っています。
広報との繋がりがない方は、X などで調べてみることをおすすめします。意外と先々のトレンドをつぶやいてくれている人や、今話題となっているものをまとめてくれている人がいます。是非ご参考ください。
メール配信を工夫する
とある統計データによると、BtoB ウェビナー においては、約7割の参加者がメール経由の申し込みと言われています。
弊社でも、基本的にはメールからの流入が多く、SNS やPeatix などで告知をしても、メールを上回ることはあまりありません。とはいえこれは業種業態によって異なりますので、人事向けであれば 日本の人事部や HR プロといった媒体を使って集客をする場合もあります。
ただし、メールはウェビナー集客を行う上で、多くの業界・企業で切っても切り離せないものですので、そのコツを3つお伝えします。
①当日の集客メールを取り入れる
ウェビナーをする際は、必ず当日の集客メールを行うようにしましょう。実は当日メールは非常に有効的で、ウェビナー集客数の3分の1を当日メールからの流入で占めることがあります。
当日メールの場合は、タイトルの冒頭に「本日〇〇時開催」という文字を入れることをおすすめします。比較的開封率が高くなる傾向があります。
②ノウハウ記事型集客メールを活用する
ウェビナー集客のセオリーとして、バナーを一番上に掲載する、あるいは 申し込みの CTA ボタンをメールの上部に掲載するというものがあります。
一方で、ノウハウ記事型集客メールは構成が異なります。具体的には下記をご覧ください。
上部にはウェビナーで話す予定のノウハウを読み物として記載し、メールの結びとして「詳細は是非ウェビナーをご覧ください」という導線で作成をするものです。
このようなメールは、開封率・クリック率ともに高い傾向にあります。是非お試しください。
③メールの内容にこだわる
ウェビナー集客メールは、HTML の形式で申し込みページをそのまま掲載する事がおすすめです。企業のスタンスや、販売する商材によっても異なりますが、昨今のウェビナー集客メールはこのような形式が多いです。
冒頭に「〇〇株式会社 〇〇様」を入れずにメールを送るのは、これまでの常識からしたら考えられませんでした。しかし、「伝えたいことを一番上に配置する」「ファーストビューは7秒しか見られない」「最初の140文字しか見られない」と言った BtoB のメルマガのセオリーを元にすると、理にかなった形式であると言えます。
年間約1.1万人集客・満足度97%!シャノンが語る、ウェビナー改善ノウハウ5選(MarkeZine / 2022.10.07)
上記3つのポイントに加えて、集客メールの最適な構成・文例・送信タイミングを以下の記事で解説しています。ご参考ください。
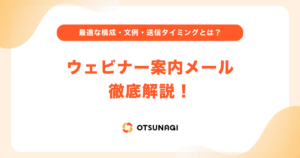
SNS告知を工夫する
X や Facebook、リンクトインなど、ウェビナー集客に活用できる SNS は様々です。フォロワー数に応じて申し込みの数はかなり変動しますが、ここではポイントを1つに絞ってお伝えさせていただきます。それは、投稿文章にリンクを入れないということです。
多くの SNS は、別サイトに遷移させることを嫌います。つまり投稿にリンクが直接貼ってあると、なかなかインプレッションが伸びづらいというアルゴリズムが働きます。
※SNSによって異なります。
例えば、 X で投稿をする時は画像のみを添付し、案内用の URL はコメント欄に添付するなど工夫をしています。是非お試しください。
営業チームに協力依頼をする
社内の営業メンバーにウェビナー集客を、手伝ってもらうことも重要です。
具体的には、見込み顧客への架電時、「今度こんなウェビナーやっているのでぜひ参加してください、メールで詳細お送りします」などと伝えたり、メールの署名欄に告知を添えてご連絡をするなど、コミュニケーションのきっかけにすることもできます。
++++++++++++++++++++++++++++
\大好評ウェビナー第2弾 来週開催/
詳細はこちら:https://www.otsunagi.co/webinar/
OTSUNAGI株式会社
代表取締役
茂木 優弥 -Yuya Mogi-
++++++++++++++++++++++++++++
また先ほどの SNSと通ずることもありますが、もし 営業メンバーに SNS を持ってる人がいたら投稿に協力してもらうように伝えてみましょう。
営業チームに協力依頼をする時のポイントは、なるべく営業メンバーに手間をかけさせないということです。営業メンバーは目の前の商談受注を目標に動いていることが多いです。直結しない動きは、やはり後回しになってしまいます。
明確に実施して欲しいことを伝え、かつなるべく手をかけないでできるように工夫をしましょう。
無料告知サイトを使う
Peatixなどの無料告知サイトは、必ず使ってください。こちらの図は無料で使えるウェビナーポータルサイトをまとめたものです。
ただし、全てに掲載をしたとしても1件しか申し込みが入らない、と言うことはよくあることです。
イベントプラットフォームはそれぞれ、SNS と同様に攻略法があるはずです。掲載すればいいというだけの話ではないので、具体的にどのように活用したらいいかは、イベントプラットフォームの担当者に聞いたり、上手く活用している人に質問してみると良いでしょう。
また、各イベントプラットフォームはイベント集客代行のサービスも持ち合わせていることが多いです。成果報酬型で集客してくれるサービスもあれば、固定額で集客代行してくれるものもあります。是非各社へ、お問い合わせしてみてください。
おすすめの集客サイトは、以下の記事をご参考ください。
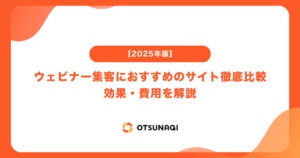
申し込みページを工夫する
やはり申し込みページの工夫は、申込者数の最大化において重要な工夫の1つです。EFOの観点で、申し込みフォームはファーストビューの右側に設置できるのが理想です。またフォームを下部に設置する場合は、アンカーリンクを使うと良いでしょう。
「こんな方におすすめ」や「概要」などは、意外と見られています。このウェビナーに参加することで何が学べるのか、どんなことを話すのかを、必ずページ内に入れるようにしましょう。
タイトル/バナーを工夫する
やはりウェビナー集客を最大化するのは、何と言ってもタイトルです。ウェビナー集客がうまくいっている会社では、メインタイトルは15文字以内に徹底しているそうです。やはり端的で分かりやすいものは、魅力的で参加したいと思われやすいです。
その他にも、いくつかタイトルをつける際の工夫をお伝えします。
- 具体的な数字を入れること
- 要素を多く含めないこと
- 分かりやすい言葉を使うこと
- タイトル内に2つ以上同じ言葉を使わないこと
- 本やテレビ、映画のタイトルなどを参考に作ること
- 流行りの言葉を使うこと
またつけたタイトルを、さらに分かりやすくするためにバナーがあります。実際に弊社OTSUNAGIで、集客が最大化できたウェビナータイトル・バナーをご紹介します。
まとめ:工夫を凝らして集客を最大化しましょう
ウェビナーの集客は、工夫次第でより伸ばすことができます。ハウスリストが少なくお悩みの方や、広告費をかけずに集客したい方は、ぜひ紹介したコツを試してみてはいかがでしょうか。
ウェビナー運営にお悩みの方や、成果を最大化したい方は、ぜひOTSUNAGI株式会社にご相談ください。OTSUNAGI株式会社は、年間100件以上のオンラインイベントを支援するウェビナー運営のプロフェッショナル集団です。企画設計からZoom設定、当日の配信オペレーション、アーカイブ活用、さらには共催企業とのマッチングまで、成果に直結するウェビナー施策を一気通貫でご支援いたします。
「社内にリソースがない」「企画が思いつかない」「共催先が見つからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOTSUNAGIにご相談ください。貴社の強みを引き出し、ウェビナーを起点とした“商談につながる仕組みづくり”を全力でサポートいたします。