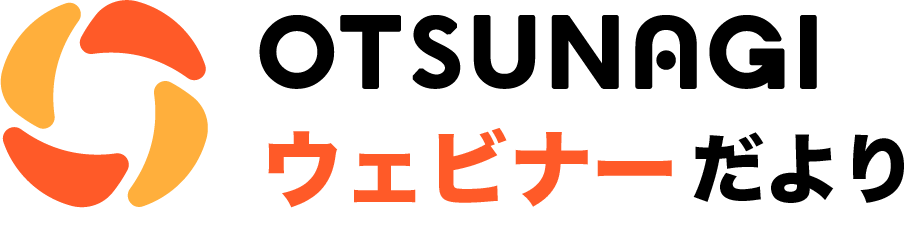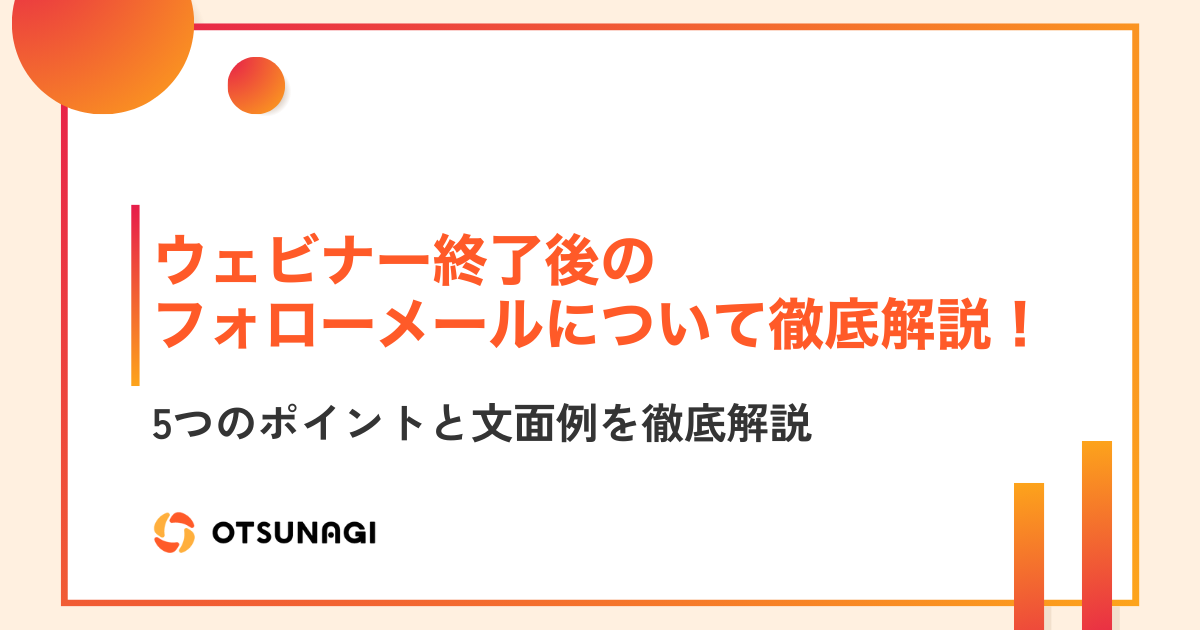ウェビナーを開催したものの、「その後のフォローメール、どうすればいいの?」と悩むことはありませんか?
お礼のひと言を添えただけで終わっていたり、テンプレートを使って送ってはいるけれど、成果につながっている実感がなかったり——。
実は、フォローメールの設計を少し工夫するだけで、ウェビナー後の反応が変わることもあります。
この記事では、ウェビナー後のフォローメールをテーマに、成果につながるメールのポイントや文面例、
さらにメール以外の効果的なフォロー方法まで、実践的な内容を解説します。
メールを「なんとなく送る」から「少しでも成果に近づける一手」に変えたい方は、ぜひご覧ください。
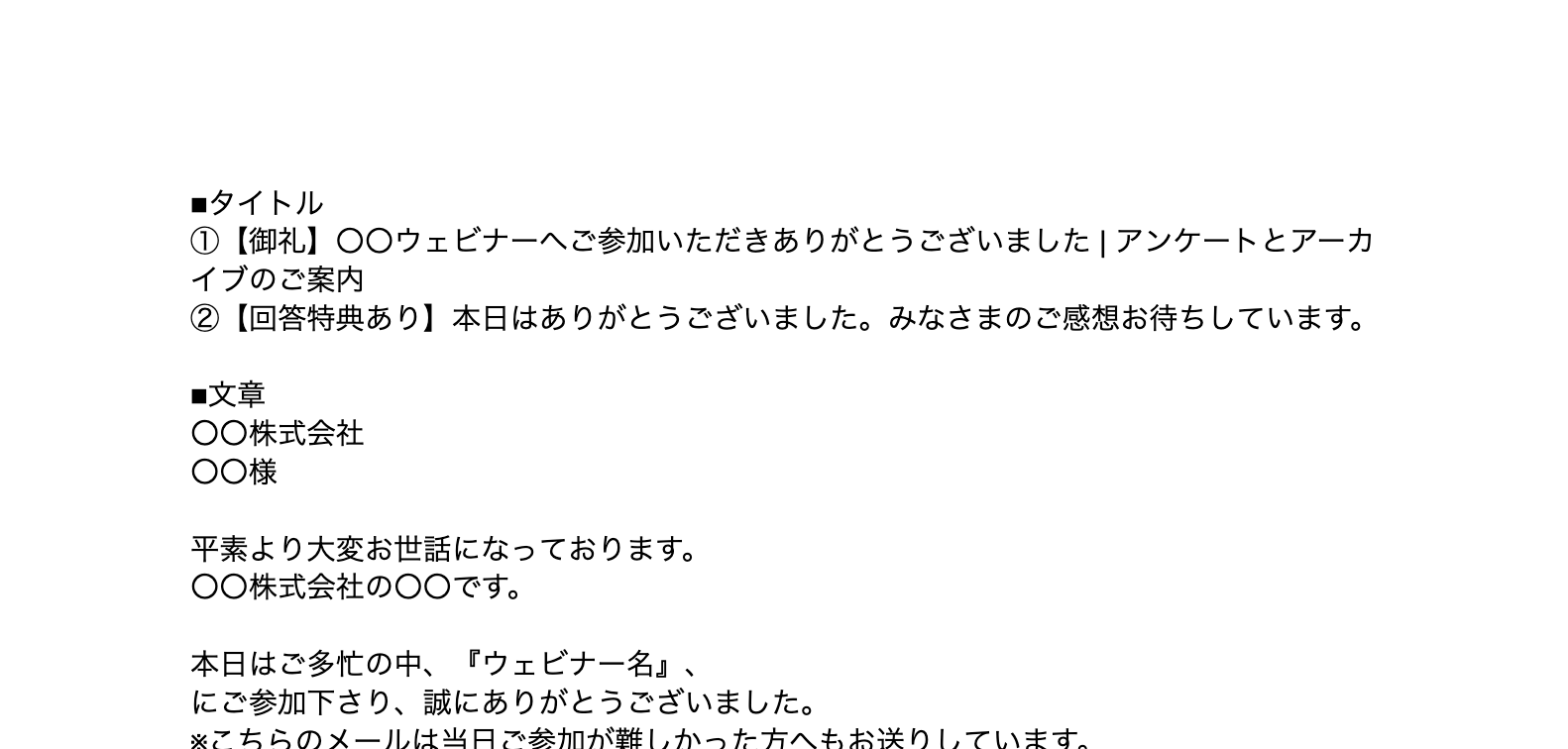
OTSUNAGI特製のフォローメールのテンプレートを無料でプレゼントいたします!
以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。
ウェビナーの効果を最大化するには「フォローメール」がカギ
フォローメールの目的とは?参加者との関係を育てる第一歩
フォローメールの目的は、参加者との関係性を深め、次の行動(商談・資料DL・アンケート回答など)につなげることです。
ウェビナーで得た関心や記憶が新しいうちに、適切なフォローを行うことで、興味を継続的な接点に変えていくことが可能になります。
単なるお礼だけで終わらず、アンケート・アーカイブ視聴・資料DLなど“次の行動”へと自然に誘導する設計が求められます。
特に、参加者が情報を覚えている“直後”のタイミングで届けることで、印象と行動が結びつきやすくなります。
「とりあえず送る」では成果につながらない
お礼のひと言だけで終わってしまうフォローメールは少なくありません。
しかし、それでは相手の関心を行動に変えることは難しいです。
具体的にはフォローメールに「アンケート」と「アーカイブ配信」の案内など、次のアクションにつながりやすい「仕掛け」を入れることをおすすめしています。
さらに、それぞれに「回答・視聴の締切日」を明記することで、行動率が上がる傾向があります。
こうした小さな設計の工夫が、成果に直結する可能性を高めてくれます。
成果を出すフォローメール5つのポイント
配信は“即日・5分以内”が理想
フォローメールはスピードが命です。
参加者の熱量が残っているうちに届けることで、メールの開封・行動率は大きく変わります。
理想はウェビナー終了後、5分以内に送付。
事前にテンプレートを用意しておいたり、やCRMシステム側で配信設定を行なっておけば、簡単に実現可能できるので、実践していない方は早速取り組んでみましょう。
件名で“開封率”を上げるシンプルなコツ
「”〇〇セミナー”へのご参加ありがとうございました|アーカイブ&アンケートのご案内」など、イベント名や具体的なアクションを含んだ件名が有効です。
対象者が「自分向けだ」と感じられるように設計しましょう。
| NG例(ありがちだけど弱い) | OK例(クリックを促す) |
|---|---|
| ウェビナーご参加ありがとうございました | 【アーカイブあり】ご参加ありがとうございました|アンケート回答のお願い |
| 先日のセミナーについて | 【期間限定視聴】●月●日開催ウェビナー アーカイブのご案内 |
| 本日の資料をお送りします | 【DL期限あり】ウェビナー資料とアンケートのご案内 |
→ ポイントは、件名の中に「何が届いているか」「いつまで見られるか」を明記すること。
ひと目で中身と重要度が伝わる件名にすると開封率も上がる可能性が高いので、ぜひ試してみてください。
本文はシンプルに、かつ意図を明確に
フォローメールの本文は「感謝」→「案内(アンケート・資料・アーカイブなど)」が基本です。
可能であれば、当日の要点を簡単にまとめて添えると記憶に残りやすくなります。
リンクには期限を明記し、「締切〇月〇日」と書くことでクリック率が上がる傾向があります。
以下にテンプレートをご用意しましたので、参考にして作成してみましょう。
CTAは“ひとつに絞る”のが効果的
フォローメールでは「何をしてほしいか」が明確であることが大切です。
複数のCTA(アンケート、資料DL、商談打診など)を並べてしまうと、受け手が迷い、かえって何もアクションしない可能性があります。
CTAは“目的に応じてひとつに絞る”のが効果的とされています。
とはいえ、「アンケート」「資料」「アーカイブ」など複数案内したいケースもありますよね。
そんな時は、ひとつのCTAに導線をまとめる工夫が有効です。
- メールでは「アンケート回答」をメインで訴求する
- アンケート完了後の完了画面やサンクスメールで、資料DLリンクやアーカイブ視聴URLを案内する
こうすることで、メールの中では1つの行動だけを促しつつ、他のアクションにも自然につなげることができます。
「アンケート回答後に、登壇資料をプレゼントします」といった訴求は特に効果的です。
不参加者にも、フォローメールは効果的
フォローアップメールは、参加者だけでなく「申込はあったが参加できなかった方」にも送るのが効果的です。
予定が合わず参加できなかった方の中にも、関心度の高いリードが含まれている可能性があります。
そのような方には、
- アーカイブ配信のご案内
- 資料のみの送付
- 次回ウェビナーの開催告知
など、“接点を継続させる”ための情報提供が有効です。
メール文面では、「ご予定が合わなかった方へ」といった一文を添えることで、押しつけがましさを軽減できます。
なお、工数がかかることがネックであれば、「参加者向け」のフォローメールと合わせて配信してもいいでしょう。
ウェビナーをきっかけとした関係構築は、参加者だけに限定せず、広くフォローしていくことが重要です。
フォローメールの文面例【参加者向け/不参加者向け】
実際に使えるフォローメールの文面例を「参加者向け」「不参加者向け」に分けてご紹介します。
メールを作る際の構成イメージやトーン、伝えるべき要素を整理する参考にしてみてください。
参加者向けメール文例(テンプレと解説付き)
件名例:
【回答特典あり】”〇〇セミナー”へのご参加、ありがとうございました | アンケートとアーカイブのご案内
本文例:
〇〇様
このたびは「●●●ウェビナー」にご参加いただき、誠にありがとうございました。
今回のウェビナーでは、以下のようなポイントを中心にお話ししました。
ぜひ振り返りの際のご参考にしていただけますと幸いです。
- 〇〇業界における最近のトレンドとユーザー動向
- ウェビナー施策における商談化率を高めるための3つの工夫
- 成功企業が実践するフォローアップの具体例
当日ご紹介した内容について、下記よりアーカイブ視聴およびアンケート回答が可能です。
今後のイベント改善にも活用させていただきますので、ぜひご協力をお願いいたします。
📺 アーカイブ視聴(※〇月〇日まで)
[リンク]
📝 アンケート回答(※〇月〇日まで)
アンケートにご回答いただいた方には本日の登壇資料をプレゼントいたします。
1分程度で回答可能ですので、ぜひご回答いただけますと幸いです。
[リンク]
今後ともよろしくお願いいたします。
文面のポイント
- 件名には「アーカイブ」「アンケート」など受け手にとっての価値が一目で伝わる要素を入れる
- 冒頭で参加へのお礼 → 当日の要点を簡潔にまとめる(可能であれば)
- アンケート回答と資料DL/アーカイブ視聴の導線を提示
- 行動のきっかけになるように、期限を明記する
不参加者向けメール文例(テンプレと解説付き)
件名例:
【アーカイブ配信のご案内】ご参加いただけなかった方へ(〇月〇日ウェビナー)
undefined
〇〇様
このたびはご登録いただきながら、ご都合により参加いただけなかったとのこと、誠に残念ではございますが、アーカイブ視聴をご用意しております。
ご都合の良いタイミングでぜひご視聴ください。要点をまとめた資料も併せてご確認いただけます。
📺 アーカイブ視聴(※〇月〇日まで)
[リンク]
📝 アンケート回答(※〇月〇日まで)
アンケートにご回答いただいた方には本日の登壇資料をプレゼントいたします。
1分程度で回答可能ですので、ぜひご回答いただけますと幸いです。
[リンク]
📄 資料DL(※〇月〇日まで)
[リンク]
ご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
文面のポイント
- 冒頭で「参加できなかったことを理解している」トーンを伝える
- 興味を持ってくれたことへの感謝を忘れずに
- アーカイブ視聴や資料DLなど、“当日参加しなくても価値が得られる導線”を提示
- 今後の案内を受け取りやすくなるよう、軽く期待感を持たせる一文を添える
メールだけじゃない!成果につながる複合的なフォロー設計
アンケートでのインサイト収集
フォローメール内にアンケートを含めることで、参加者の興味関心や自社課題のヒントを得ることができます。
回答内容によっては、次回ウェビナーのテーマ設計や営業のトーク設計にも活用できる貴重なデータとなります。
特に、「導入予定時期」「検討中の課題」などを設問に入れておくと、見込み客の温度感を把握しやすくなります。
電話やチャットでのクイックフォロー活用例
メールに反応してくれた方や、アンケートで温度感の高い回答をくれた方には、
メールだけでなく、電話やチャットでのクイックフォローも有効です。
「●●について詳しく知りたい」などの反応がある場合、undefined軽くヒアリングするだけでも商談化の糸口になることがあります。
可能であれば、全てのリードに対してアクションをとるのが理想です。
とはいえ人的リソースに限りがある場合は、役職や企業規模、自社との親和性の高い業種などを基準に優先順位をつけて、段階的に接触を進めるのがおすすめです。
フォローメールを活用してセミナーの成果を最大化しよう
ウェビナー後の対応は、ちょっとした設計の差で成果に大きな違いが生まれます。
「いつ、誰に、どのようなメールを送るか」「アンケートやアーカイブはどう伝えるか」など、実践的な工夫が結果に直結します。
もし今、「自社に合ったフォローアップの型が見つからない」と感じている方は、ぜひお気軽にOTSUNAGI株式会社にご相談ください。
OTSUNAGI株式会社は、年間100件以上のオンラインイベントを支援するウェビナー運営のプロフェッショナル集団です。企画設計からZoom設定、当日の配信オペレーション、アーカイブ活用、さらには共催企業とのマッチングまで、成果に直結するウェビナー施策を一気通貫でご支援いたします。
「社内にリソースがない」「企画が思いつかない」「共催先が見つからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOTSUNAGIにご相談ください。貴社の強みを引き出し、ウェビナーを起点とした“商談につながる仕組みづくり”を全力でサポートいたします。
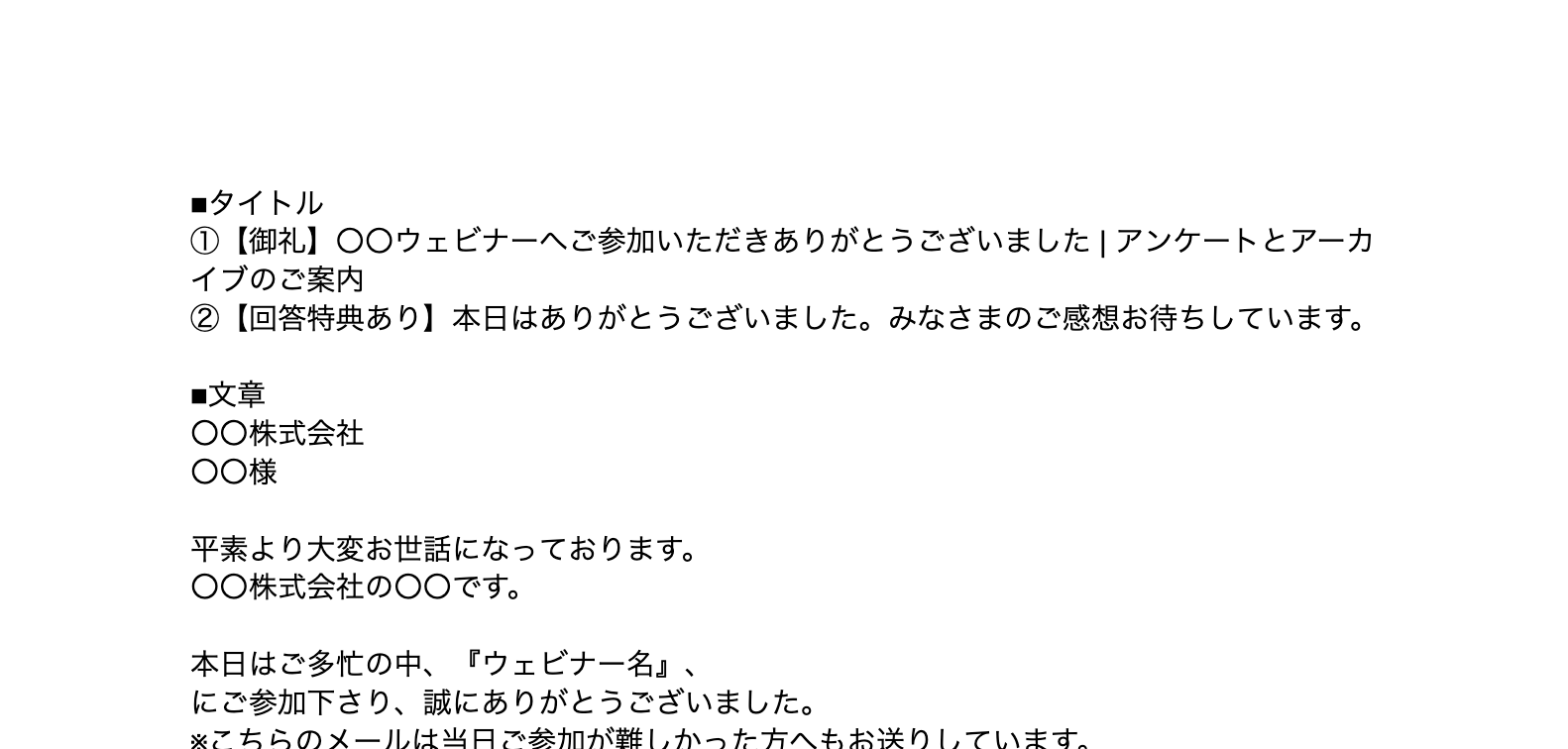
OTSUNAGI特製のフォローメールのテンプレートを無料でプレゼントいたします!
以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。